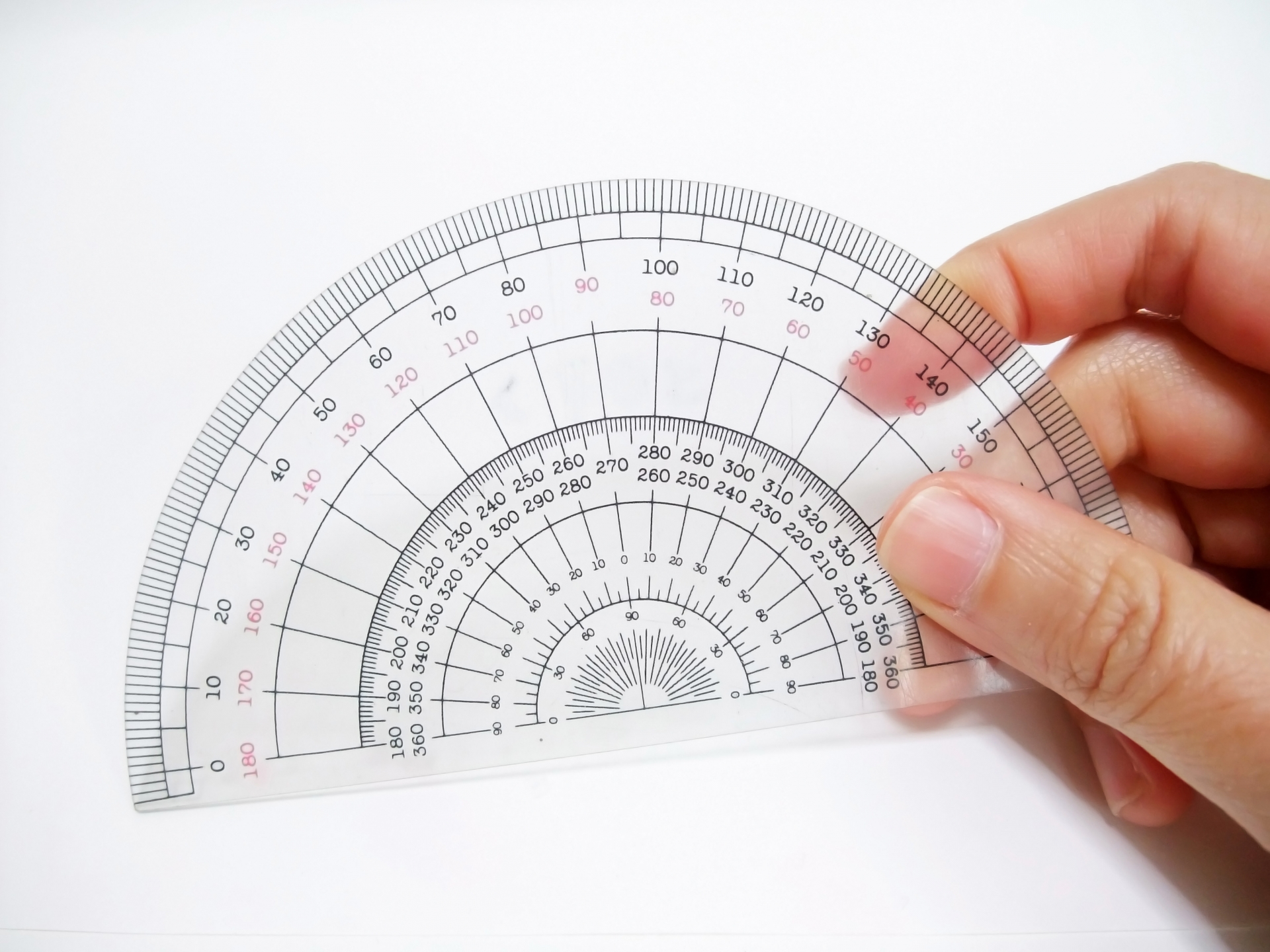子どもでもできる!分度器なしで角度を測るコツと作り方|親子で楽しむかんたん算数
「分度器が見つからない…」「宿題で角度を測らないといけないのに困った!」そんなときでも大丈夫です。身近な道具や少しの工夫で、分度器がなくても角度はしっかり測れます。この記事では、紙折り・三角定規・コンパス・スマホなどを使った具体的なやり方を、やさしい言葉でていねいに紹介します。親子で試しながら、算数をもっと身近に感じてみましょう。
分度器がなくても測れる理由と基本アイデア
角度は「既知の角度と比べる」「角を半分にする(角の二等分)」「形の性質を使う」の3つで作ったり測ったりできます。まずは基準になる角度をいくつか覚えると、とてもラクになります。
日常にある“基準角”をものさしにする
- 本・ノートの角=直角(90°)
- 正方形の対角線と辺の角=45°
- 正三角形の角=60°(折り紙で作りやすい)
- 時計の短針・長針が12と2で作る角=60°、12と1で作る角=30°(ざっくりの目安)
これらと「比べる」だけで、おおよその角度がわかります。
角の二等分で細かい角度を作る
角を半分に分けると、45°・30°・15°…と細かく作れます。紙でもコンパスでもできます。
紙折りで角の二等分(手順)
- 直角(90°)を作る:紙を十字に折るだけでOK。
- 45°を作る:90°の紙角をさらに半分に折る。
- 22.5°・67.5°を作る:45°をもう一度半分に折る(細かい角度の目安に便利)。
コンパスで角の二等分(手順)
- 角の頂点にコンパスの針を置き、2本の辺と交わるように弧を描く。
- 交点2か所をそれぞれ中心にして弧を描き、交わったところと頂点を直線で結ぶ。
- その線が角の二等分線(角をぴったり半分)になります。
方眼紙・格子を使う(見た目+比で測る)
- 1マス右に4、上に4進む線は45°、1マス右に3・上に5など比で角度の目安が作れます。
- 3:4:5の直角三角形を作ると、直角の確認にも役立ちます。
基準角:作り方の例 ーーー 使うもの 精度の目安
90° :紙の角/本の角 ーーー 紙・本 高い
60° :正三角形を作る・時計の12と2 ーーー 折り紙・時計 中〜高
45° :正方形の対角線/90°を半分 ーーー 紙・定規 高い
30° :60°を半分(角の二等分) ーーー 紙・コンパス 高い
15° :30°を半分(角の二等分) ーーー 紙・コンパス 中〜高
身近な道具でできる測り方(手順つき)
三角定規で測る・作る
- 30°・60°・45°・90°の角が最初から入っています。測りたい角に当てて比べるだけ。
- 「45°より広い?狭い?」のように基準と比べると判断が早くなります。
45°の線を引く(定規だけバージョン)
- 正方形を描く(たて横の長さを同じにする)。
- 対角線を引くと、その線と辺の角が45°になります。
コンパスで作る角
- 60°:中心から同じ半径で円周上に点を打ち、正三角形を作ると各角が60°。
- 30°:60°を角の二等分で半分にする。
- 等しい長さを保てるので、誤差を小さくしやすいのが長所です。
紙の折り目で作る角
- 90°:紙を十字に折れば簡単。
- 45°:90°の角をさらに半分に折る。
- 22.5°・67.5°:45°をもう一度半分に折る。
- 60°近く:紙を3つ折りにして目安に(正確ではないが目安として有効)。
スマホ・デジタルツールの活用
角度計アプリのタイプ
- 画面合わせ型:画面上の線に合わせて角度を表示。
- カメラ重ね合わせ型:カメラ越しに対象物へ線を重ねて角度を表示。
- 水平器型:スマホ自体の傾きを角度で表示(棚板・額縁の水平確認に便利)。
正確に測るコツ
- スマホを机・壁にしっかり当てる(スキマや傾きに注意)。
- キャリブレーション(補正)機能で0°を合わせる。
- ケースの厚みやカメラの出っ張りでズレやすいので、当てる位置を一定にする。
方法:準備のしやすさ ーーー 精度 おすすめ場面
紙を折る:とても簡単 ーーー 中〜高 家庭学習・自由研究
三角定規:簡単 ーーー 高い 宿題・工作の下書き
コンパス:ふつう ーーー 高い 図形の作図・検算
スマホアプリ:簡単 中〜高 ーーー 家具・斜面の角度確認
具体例でマスター!欲しい角度の作り方
45°・60°を分度器なしで作る
- 45°:正方形を描いて対角線を引く。紙折りなら直角を半分に折る。
- 60°:正三角形を作る(同じ半径の弧を3回移し、3点を結ぶ)。
50°や55°を近似する(補間の考え方)
- 50°:45°と60°の間。45°に対して少し広げる(1/3〜1/2くらいの感覚)。
- 55°:60°から少し狭める。60°→55°は5°の差なので、ほんの少しだけ内側へ。
- 検算のコツ:同じ角を2つ合わせて直線(180°)や直角(90°)にどれくらい近いかを比べると感覚がつかめます。
15°・30°・75°など細かい角度の作り方
- 30°:60°を二等分。
- 15°:30°を二等分。
- 75°:90°から15°を引く(90°と15°を作って重ねて判断)。
- 22.5°:45°を二等分。67.5°=45°+22.5°も作れます。
欲しい角度: 作り方の例 ーーー 使うもの ポイント
30° :60°を半分 ーーー コンパス or 紙 角の二等分を活用
50° :45°と60°の中間 ーーー 三角定規・紙 中間をねらう補間
55° :60°から少し狭く ーーー 三角定規・紙 5°の差はごく小さい
75° :90°−15° ーーー 紙・コンパス 引き算で作る
22.5° :45°を半分 ーーー 紙 細かい目安に便利
誤差を小さくするコツと“あるある”解決
誤差を減らす基本
- 長い定規・長い辺を使う(線が長いほどずれにくい)。
- 線は細く、鉛筆の先をとがらせる。太い線は読み取りがぶれます。
- 目の位置は真上・真正面。斜めから覗くと視差でずれます。
- 紙はしっかり押さえる。折り目は爪や定規でしっかりスジをつける。
よくあるつまずきと対策
- 紙がずれて正確に半分にならない → 折る前に辺や角をきちんと合わせ、折った後は定規でしごいて折り目をくっきり。
- 三角定規がすべる → 下に紙を1枚敷く/ノンスリップの輪ゴムを軽く巻く。
- コンパスがずれる → 少し大きめの半径で描くと交点がはっきりし、精度が上がります。
家庭学習・自由研究で試したいアイデア
角度ビンゴ
- 45°・60°・30°・90°などの角を作ってビンゴ表を作成。家の中でその角度に近いものを探してマーク。
身近なものの角度調べ
- 本棚の傾き、坂道の角度、イスの背もたれの角度などを紙・定規・スマホで測って記録し、表にまとめる。
検算ノートを作る
- 作った角を組み合わせ、直線(180°)・三角形(180°)・四角形(360°)で合計を確認して精度をチェック。
まとめ|分度器がなくても角度は作れる・測れる
直角や60°などの“基準角”を使い、二等分や補間で細かい角度を作れば、分度器がなくても十分に角度を扱えます。紙・三角定規・コンパス・スマホなど、状況に合わせて道具を選び、誤差を小さくするコツを押さえれば安心です。親子で楽しく試しながら、角度の感覚を育てていきましょう。
分度器なしで角度を測る時に便利な道具チェックリスト
- 折り紙・ノート(直角・二等分・45°づくり)
- 三角定規(30°・45°・60°・90°の基準)
- 定規(直線を長く引いて誤差を減らす)
- コンパス(60°・二等分・作図の精度アップ)
- スマホの角度計アプリ(家具・斜面の角度確認)
- 本・箱・机など直角の出る日用品(基準づくり)